文字
背景
行間

SGH活動報告
1学年課題研究クラス発表会開催
12月22日(火)、1学年普通科7クラスはクラス単位で発表会を開催しました。4人を標準とする70の研究班が初めて聴衆の前でプレゼンテーションをしました。本校の課題研究は研究テーマの制約はありません。よってニッチでユニークな発表がたくさん登場しました。もちろん研究の質もプレゼンの能力もまだまだです。これから1月下旬の学年発表会、2月上旬の佐倉高校課題研究発表会に向けてブラッシュアップが続きます。



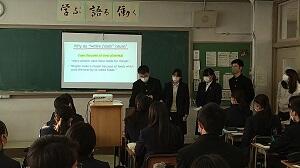
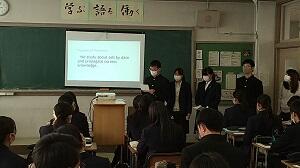




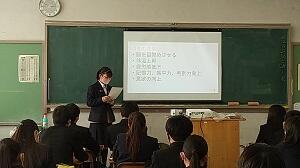



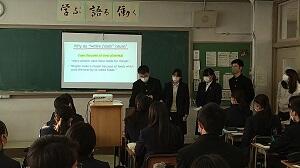
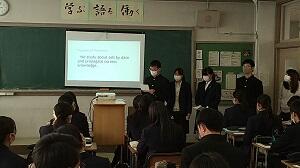




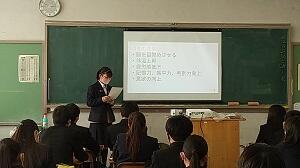
SGH 2020全国高校生フォーラム開催
12月20日(日) 2020年度全国高校生フォーラム が開催されました。
本校参加チームの要約を紹介します。
【Title】 Infectious Diseases and Climate Change
【Title】 Infectious Diseases and Climate Change
【Outline】
Though both infectious diseases and climate change are crises, the world is doing nothing to fundamentally solve them. So, we tried to find an underlying factor of these two crises because we knew that social issues are closely related to each other. After careful consideration, we’ve found that meat consumption is one of those. And we think that we need to change our daily diets. So, we made a poster that shows how meat consumption affects these crises and distributed them. In addition, we did a campaign “plant-based photo contest” to encourage taking actions and to share our idea.


Though both infectious diseases and climate change are crises, the world is doing nothing to fundamentally solve them. So, we tried to find an underlying factor of these two crises because we knew that social issues are closely related to each other. After careful consideration, we’ve found that meat consumption is one of those. And we think that we need to change our daily diets. So, we made a poster that shows how meat consumption affects these crises and distributed them. In addition, we did a campaign “plant-based photo contest” to encourage taking actions and to share our idea.


夢の図書館ワークショップ
12月10日(木)、新しく建設される佐倉市図書館&複合施設の活用を巡るワークショップが本校で開催されました。佐倉市役所の主催のもと、千葉大学で建築学を学ぶ学生8名と本校生徒9名が、3つのグループに分かれ、話し合いと発表を行いました。高校生のアイデアが次々と生まれるよう、大学生が会話をリードし、付箋を使い整理していきました。「高校生の部活や課題研究を発表するスペース」「森や暖炉を眺めながらの読書スペース」「食をテーマに老若男女が集う空間」など、50枚を超えるアイデアが付箋にまとめられました。これらの提案は、今後、市役所や設計事務所の計画に活かされる予定です。また建築を学ぶ大学生との知的会話から、生徒たちは大いに刺激を受け、ワークショップ終了後も質問が途切れませんでした。







令和2年度 海外理解促進のための講演会
11月20日(金)、1年生が、海外経験豊富なお二人の講師のお話を伺いました。稲葉健一氏(演題「グローバル化と国際協力」)は、青年海外協力隊員としてパラグアイでコミュニティー開発に携わった経験や、大学、会社勤めを経て青年海外協力隊に応募するまでの経緯を中心に話されました。現地での生活や地元の様々な立場の人とのコミュニケーションから、何が必要かを考え、伝え方を考え、小さな改善を積み重ねていくことの重要性や、「無い」からできないと諦めてはいけないことなどを話していただきました。遠藤恭一氏(演題「未来を切り拓く力とは-グローバルかとコロナ禍後の世界-」)は、人生100年時代、1つの会社や日本国内のみで働くことは益々少なくなっていくであろう時代、AIにはできない「次に何をするか、問題は何か」を探す力が問われる時代に向けてどう備えるかというお話でした。自ら意識してより広い世界を見ようとする姿勢や、「何を考えているのか、なぜそう思うのか」言葉で自己主張ができる習慣をつけること、少し雑でもよいから臆せず行動してみること等、大変刺激を受ける内容でした。講演後の質疑応答も活発に行われ、考えを深める機会となりました。
また、この講演会に先立ち、11月17日(火)から在籍することになったスイスからの留学生が1年生に紹介されました。来年7月末まで滞在しますのでよろしくお願いします。


SGH講演会「世界についてのステレオタイプをどう克服するか」
10月27日(火)、東京外国語大学教授の青山弘之氏をお招きし、1年生を対象に「気付く・探る・考える」講演会を開催しました。「世界についてのステレオタイプをどう克服するか:西アジア・北アフリカ・中央アジア地域をめぐって」が演題でした。私たちは西アジアの未知な出来事を「イスラーム〇〇」とひとくくりにし、ステレオタイプを押しつけているのかもしれません。未知なもの、複雑なもの、理解が困難なものを、「イスラーム」というレッテルを貼り誤魔化してしまうのが、ステレオタイプの弊害です。既知のステレオタイプを多様なイスラームの人々に当てはめないこと、それが共存のコツです。情報が瞬時に駆け巡るグローバリズムの実態、世俗主義とはなんなのか、表現の自由とは、多文化共生とはなんなのか。考えを深める要素が満載の講演会でした。





